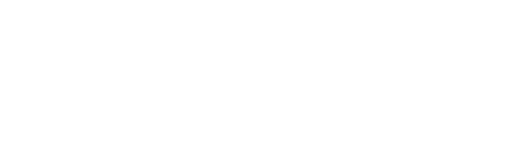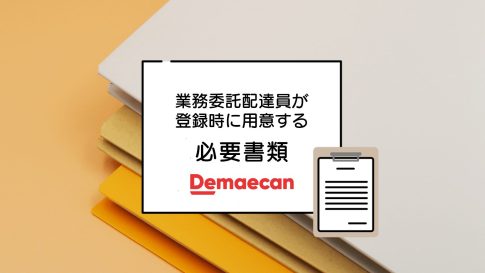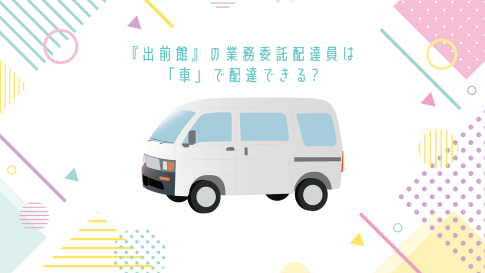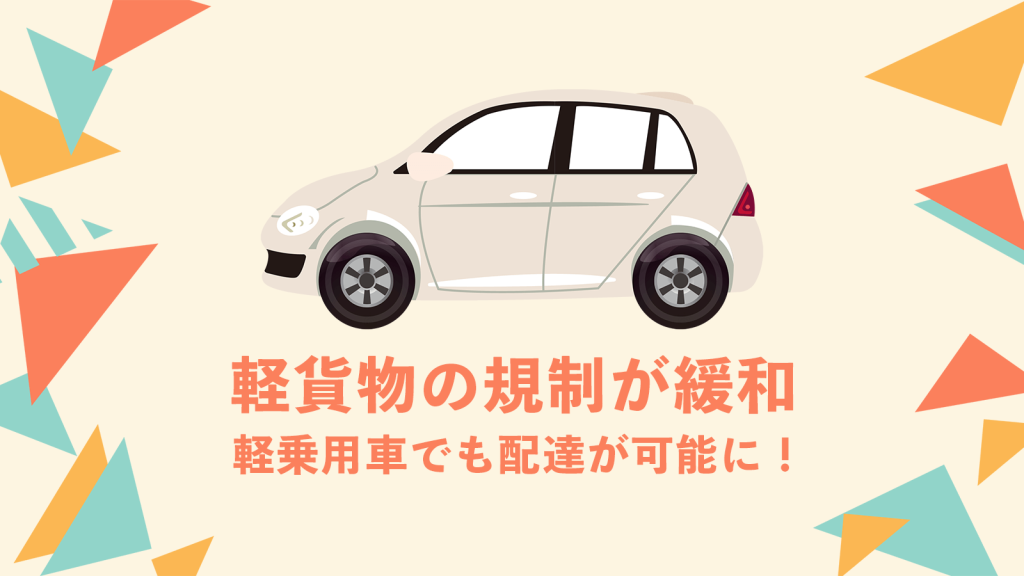
2022年10月~、貨物軽自動車運送事業法の内容が変更となり規制が緩和されました!これにより、フードデリバリーサービスの配達時に、新たに車両を購入したり改造することなく、正しく申請すれば家庭用の軽乗用車でも配達が可能となりました。
- 申請にはどんな書類が必要なの?
- 軽貨物での配達についての注意点が知りたい!
といった、新たに緩和されて可能になった軽乗用車で黒ナンバーを取得する方法などを詳しくご紹介していきます。

目次
- 1 家庭用の自動車でも配達が可能になった!
- 2 黒ナンバー取得が可能なナンバー
- 3 軽貨物での配達を始めるためのステップ
- 4 ①運輸局へ軽貨物事業届出の提出
- 5 ②軽自動車検査協会で黒ナンバーの交付申請
- 6 ③任意保険の切り替え
- 7 軽貨物での配達を始めるために必要な書類
- 8 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 9 運賃料金表
- 10 運賃料金変更届出表
- 11 事業用自動車等連絡書
- 12 軽貨物での配達時に注意すべきポイント
- 13 車両に名称、氏名または記号を表示
- 14 稼働前の点呼
- 15 過積載運行の禁止
- 16 軽貨物での配達を行うメリット
- 17 天候に左右されずに配達できる
- 18 体力の消耗が少ないから長時間配達できる
- 19 悪路でも商品を安全に届けられる
- 20 まとめ
家庭用の自動車でも配達が可能になった!
このたび、2022年10月に貨物軽自動車運送事業法の規制緩和が行われ、このことにより家庭用の軽乗用車でも配達が可能になりました!
新しく車両を購入することなく、お手持ちの自家用車でも一定の条件下で配達が可能です。
黄色や白ナンバーなどでの配達は違法です。家庭用の軽乗用車であっても、配達を行う際には黒ナンバーの取得が必須となりますのでご注意ください。
黒ナンバー取得が可能なナンバー

赤枠部分の「分類番号」が以下の番号からはじまるナンバーであれば黒ナンバーの取得が可能です。
- 4ナンバー:小型乗用車(軽バン)
- 5ナンバー:小型乗用車(軽乗用車)
- 7ナンバー:小型乗用車(軽乗用車)
規制緩和前は4ナンバーのみしか黒ナンバーを取得できませんでしたが、緩和後は5ナンバー、7ナンバーも黒ナンバーが取得可能となりました!
軽貨物での配達を始めるためのステップ
軽貨物での配達を始めるためのステップを以下でご紹介していきます。
- 運輸局へ軽貨物事業届出の提出
- 軽自動車検査協会で黒ナンバーの交付申請
- 任意保険の切り替え
①運輸局へ軽貨物事業届出の提出
まずは、ご自分のお住まいの地域の運輸支局へ行き、開業届を提出しましょう。受理自体は15分もあれば済むようですので、「事業用自動車等連絡書」を受け取りましょう。
②軽自動車検査協会で黒ナンバーの交付申請
「事業用自動車等連絡書」を提出し、車検証の記載変更手続きを行います。
黒ナンバープレートを受け取れば交付申請は完了です!ここまでの手続きは半日もあれば完了してしまいます!
- 車検証原本
- 申請依頼書
- 黄色ナンバープレート2枚
- 経由印が押された事業用自動車等連絡書
- ナンバープレート代(1,500円)
- 認印
- 本人名義でない場合は住民票
③任意保険の切り替え
今まで加入していた任意保険は、自家用車両のものかと思いますので、事業用車両の保険に切り替えましょう。
登録しているフードデリバリーサービスによって任意保険の内容が異なるかと思いますので、しっかりと確認して保険の切り替えを行いましょう。
軽貨物での配達を始めるために必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の計2部)
- 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
- 運賃料金変更届出表(提出用・控え用の計2部)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)
- 印鑑証明
貨物軽自動車運送事業経営届出書
まずはコチラからダウンロードしてください。
- 提出先の運輸支局名
- 届け出日
- 開始予定日
- 名前/住所/電話番号
- 営業所名(住所に同じにチェック)
- 最大積載量(軽バン:350kg/軽乗用車:165kg)
- 駐車場(自宅の場合はチェックを入れ0km)スペースは約15㎡
- 休憩や睡眠のための収容能力(自宅の部屋のサイズを記載)
- 該当の運送規約にチェック
- 所属営業所名/責任者名(本人の名前を記載)
- 署名(/捺印)
運賃料金表
まずはコチラからダウンロードしてください。提出用と控え用の2部を用意しましょう。
- 距離制運賃表
- 時間制運賃表
- 諸料金
- 運賃割増率
- 運賃料金適用方法
運賃料金変更届出表
まずはコチラからダウンロードしてください。提出用と控え用の2部を用意しましょう。
- 提出先の運輸支局名
- 届け出日
- 名前/住所/電話番号
- 開始予定日
- 署名(/捺印)
事業用自動車等連絡書
まずはコチラからダウンロードしてください。提出用と控え用の2部を用意しましょう。
- 名前
- 住所
- 所属営業所名(本店)
- 使用の本拠の位置(使用者の住所と同じ)
- 自動車登録番号等(車検証と同じ)/軽に○
軽貨物での配達時に注意すべきポイント
軽貨物での配達時に注意すべきポイントは以下の通りです。1つずつご紹介していきます。
車両に名称、氏名または記号を表示
大きさやフォーマットについての指定は記載がないため、稼働時にはマグネットなどに名前を記載したものを貼り付けるで問題ありません。
稼働前の点呼
稼働前にアルコールチェッカーなどで酒気帯びや疲労の有無などをチェックする必要があります。また、車両点検などもして記録する必要があります。
過積載運行の禁止
過度な積み込みや、運転時に視界が妨げられるような場所に荷物を置くなどの行為は禁止されています。乗用車使用の場合の積載可能な重量 (乗車定員-乗車人数)×55㎏。
軽貨物での配達を行うメリット
では、軽貨物で配達を行うとどのようなメリットがあるのでしょうか?以下で1つずつご紹介していきます。
天候に左右されずに配達できる
軽貨物での最大のメリットといってもいい、天候を気にせず配達を行うことができます!悪天候時は、自転車やバイクでの配達を行う人にとっては、体力と事故への危険性との闘いです。
その分、軽貨物で配達を行えば雨風にさらされるのは商品の受け取りと受け渡し時のみ。悪天候時には配達員の数が減るため、ブーストなどが発生しやすくなります。
余分な体力を使わず配達ができるため「今日は天気が悪いから配達はやめておこう」といった機会損失を防ぐこともできます!
体力の消耗が少ないから長時間配達できる
フードデリバリーサービスにもよりますが、ほとんどのサービスは距離によって報酬が変動します。そのため、長距離の配達をコンスタントにこなすことが報酬アップのカギとなります。
自転車やバイクであれば小回りが利き、街中での配達には分がありますが、長距離配達でガッツリ稼ぎたい!という場合には他の車両よりも軽貨物での配達の方が圧倒的に体力の消耗が控えられます。
悪路でも商品を安全に届けられる
自転車やバイクのように、直に道路状況の影響を受けてしまう車両と違い、軽貨物での配達であれば振動などを軽減することができます。
また、温かいものと冷たいものを同時に運ぶ場合など、同じバックの中で仕切っているより、軽貨物の方がスペースを確保することができるため、品質をキープすることも可能。
揺れで商品がぐちゃぐちゃになったり、商品が冷たくなるという事態を減らすことができるため、お客さまからのクレームに繋がることも防げますね。
まとめ
この貨物軽自動車運送事業法の規制緩和により、今まで軽貨物での配達を諦めていたという人でも正しく申請すれば、お手持ちの家庭用軽乗用車で配達が可能になりました!
最初は少しだけ用意する書類や申請の手続きが必要になりますが、それ以上に軽貨物で配達するメリットはたくさん!これからガッツリ稼ぎたいという人には朗報ですね。
ぜひ、黒ナンバーを取得して、長時間や悪天候時の配達にも有利な軽貨物での配達をしてみませんか?